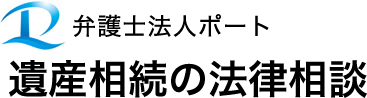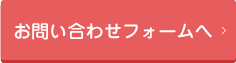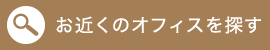遺言とどう違う?死因贈与の基本知識
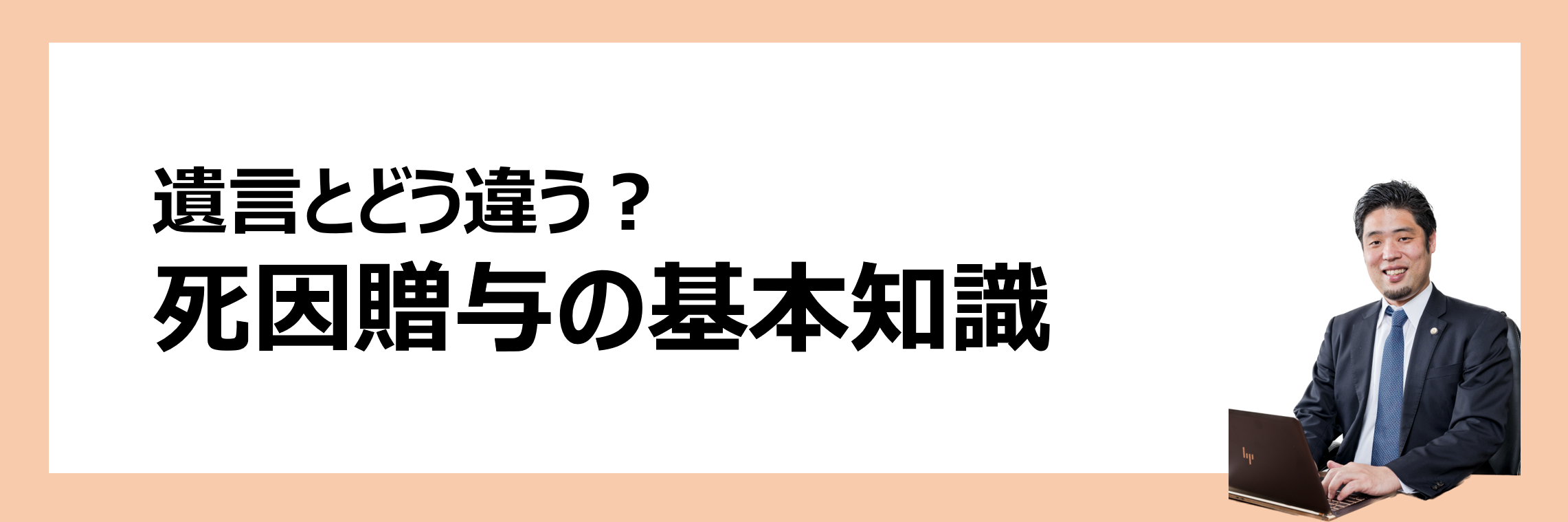
自身の死亡と同時に自己の財産を他人に移転する方法として、遺言によって財産を移転する「遺贈」のほかに、「死因贈与」というものがあります。この記事では、死因贈与制度ついてまず押さえておくべき基本知識について弁護士が解説します。
死因贈与とは
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約(目的物を無償で譲渡する契約)のことをいいます。
死因贈与と生前贈与
これに対し、贈与者が生きているうちに効力を生ずる贈与契約のことを生前贈与と言います。
例えば、AさんがBさんに不動産を死因贈与したとき、Aさんが死亡して初めて不動産はBさんの所有物となります(これに対し、生前贈与ではAさんの生前から不動産はBさんの所有となります)。
- 死因贈与:贈与者が亡くなった時点で贈与の効力が発生
- 生前贈与:贈与者の生前(多くは贈与契約の時点で)に贈与の効力が発生
死因贈与と遺贈
死因贈与と似た制度として、遺贈という制度があります。遺贈は、遺言者が遺言によって自己の財産を特定の人(受遺者)に取得させる単独行為です。
遺言者が死亡した時点で財産移転の効力が発生するという点は死因贈与と共通していますが、受遺者との合意による必要はないという点が異なります。
- 死因贈与:贈与者と受贈者の合意が必要
- 遺贈:遺言者と受遺者の合意は不要(但し、受遺者が遺贈を放棄することは可)
死因贈与の特徴
死因贈与制度について理解をするためには、まず、死因贈与の次のような2つの側面を見ておく必要があります。
死因贈与はあくまで契約であるという側面
まず重要なのは、死因贈与はあくまで贈与者(財産を与える側)と受贈者(財産を受け取る側)との意思の合致によって成立する「契約」であるという点です。
つまり、受贈者の承諾がない限り、死因贈与契約はそもそも成立しません。これに対し、遺贈は、遺言者による遺言という一方的な行為によって成立します(もっとも、受遺者において遺贈を放棄することはできます)。
死因贈与が実質的には遺贈と同様の機能を持つという側面
他方、死因贈与は、贈与者が死亡した時に初めて受贈者に財産が移転しますので、この点では遺贈と似ています。このような類似性があるため、民法は、死因贈与については、その性質に反しない限り遺贈に関する規定を準用することを規定しています。
第五百五十四条(死因贈与)
- 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
契約としての死因贈与
死因贈与契約の締結方式は自由
自筆証書遺言や公正証書遺言について解説したとおり、遺言は、民法で定めた方式に従って作成したものでない限り、無効となってしまいます。
これに対し、死因贈与はあくまで契約ですので、特定の方式による必要はありません。死因贈与契約書は私署証書で十分であり、公正証書による必要はもちろんありません。死因贈与契約書がパソコンで作成されたものであっても構いません。極論すれば、死因贈与は口頭による口約束によっても成立します(ただし、口約束では、贈与者の死亡後、これを証明することが困難となってしまいますので、書面によりその内容を確認しておくべきでしょう。)。
親権者の同意があれば15歳未満でも締結可能
民法は、有効な遺言を作成するために必要な遺言能力は、15歳以上の者に認められると規定する一方で、法定代理人である親権者による遺言を認めていないため、15歳未満の者は遺言を作成することはできません。
これに対し、死因贈与はあくまで契約であるため、親権者の同意がある限り未成年者も死因贈与の当事者となることができます。親権者が未成年者の法定代理人として死因贈与契約を締結することもできます。他方、この同意を得ることなく未成年者が単独でした死因贈与契約については、原則として親権者が取り消すことができます。
遺贈の規定の準用と死因贈与
贈与者の生前における最終の意思をできるだけ尊重すべきとの価値判断は、遺贈における遺言者のそれと同様です。このため、民法は、死因贈与につては遺贈に関する規定を準用し、次のような点について、死因贈与について通常の契約とは異なる取り扱いをしています。
死因贈与契約の撤回
契約は、その成立によって双方を拘束するものであるため、本来であれば、一方当事者の自由な意思によって契約を撤回することはできません。しかし、死因贈与については、原則として贈与者が自由に契約を撤回することができるとされています。なお、受贈者については、原則どおり、自由に死因贈与契約を撤回することはできません。
ただし、贈与者からの撤回であっても、受贈者が財産を取得する前提条件として、受贈者に対して生前に何らかの負担を課している場合(負担付き死因贈与契約といいます)であって、受贈者がかかる負担を履行していたときには、贈与者の自由な撤回が制限されることもあります。これは、いくら贈与者の最終意思を尊重すべきとはいえ、受贈者の利益を一切無視するのは妥当ではないという価値判断が働くためです。
遺言執行者の規定
遺言執行者の規定は死因贈与の場合にも準用されると考えられています。したがって、不動産の死因贈与契約書に執行者の指定があれば、受贈者が登記権利者・遺言執行者が登記義務者となり、受贈者に対する所有権移転登記手続きを行うこととなります。なお、遺言執行者がない場合には、相続人の全員が登記義務者となります。
始期付き所有権移転仮登記
なお、受贈者の権利を保全する方法として、贈与者の生前に、贈与者の死亡を始期とした贈与を原因とする所有権移転仮登記を行うことできます。仮登記とは、本登記の前にこれを行っておくことで、その後の本登記の際に登記順位を保全することのできる登記です。遺贈については仮登記を行うことができませんので、この点は遺贈との違いということになります。
受贈者が先に死亡した場合
通常の贈与契約は、受贈者が死亡してもその地位を受贈者の相続人が引き継ぎます。しかし、死因贈与契約では、「遺言者よりも先に受遺者が死亡した場合、遺贈はその効力を生じない」旨を定めた遺言の規定が準用され、先に受贈者が死亡した場合には死因贈与の効力は生じないこととなると考えられています。
まとめ
以上、死因贈与の基本的知識について解説してみました。死因贈与契約は、比較的自由な方式によって締結することができる上、遺言と同様の機能を果たすという特徴があり、この特徴をうまく生かすことによって幅広い相続対策を行うことが可能となる場合もあります。
弁護士法人ポートでは、死因贈与契約に関するご相談・ご依頼をお受けしております。本記事をお読みになり、死因贈与契約についてご不明な点がある方は、ぜひ当事務所の無料法律相談をご利用ください。