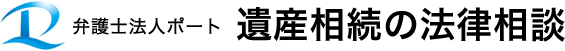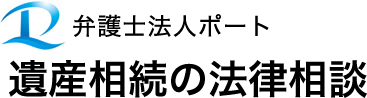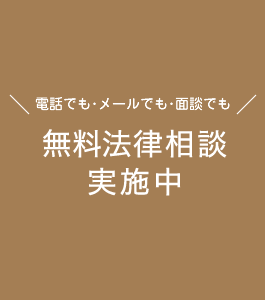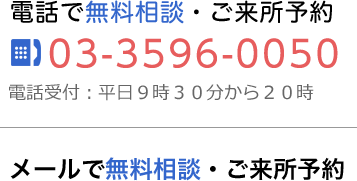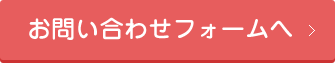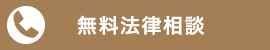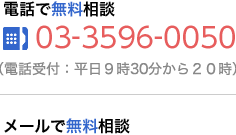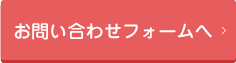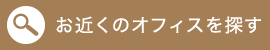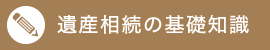生命保険金と特別受益についての判例
先日、父(A)が亡くなりました。母はすでに死亡しているため、相続人は私(X)、と弟(Y)、妹(Z)の3名です。父の遺産としては、2棟の不動産に加え、預貯金と有価証券があり、その総額は6000万円程度です。そのほか、父は生前、父を被保険者とし、妹を受取人とする死亡保険金6000万円の生命保険に加入していました。父の遺産分割に際し、妹が受け取る保険金は特別受益として扱われるのでしょうか。判例の考え方を教えて下さい。
はじめに
被相続人が相続人の一人を受取人として生命保険契約を締結し、その後被相続人が死亡したことにより相続人が多額の生命保険金を受け取った場合、その保険金は特別受益として持ち戻し計算の対象となるでしょうか。もしこれが特別受益に当たるとすれば、遺産分割における具体的相続分の算定や、遺留分減殺請求における各人の遺留分額の計算に影響することになります。
そこで、以下では、共同相続人の一部を受取人とする死亡保険金と特別受益の関係について判示した最高裁判所平成16年10月29日決定(最高裁判所民事判例集58巻7号1979頁)のポイントを解説し、同決定を前提として死亡保険金の特別受益性について判断された裁判例を紹介します。
最高裁判例のポイント
最高裁判所平成16年10月29日決定は、共同相続人の一部を受取人とする養老保険契約に基づく死亡保険金請求権について、別の相続人が、これを特別受益(持ち戻し計算の対象)とすべきであると主張した事案です。
死亡保険金は原則として特別受益とはならない
最高裁は、このような事案において、まず、死亡保険金請求権は原則として民法903条1項の特別受益には当たらないと判断しました。その理由は次の2点であるとします。
- 被相続人が自己を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人と指定して締結した養老保険契約に基づく死亡保険金請求権は、その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく、これらの者の相続財産に属するものではない
- 死亡保険金請求権は、被保険者が死亡した時に初めて発生するものであり、保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであるから、実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることはできない。
これは要するに、法形式の観点からも、経済的実質的側面からみても、生命保険金の受取人指定は遺贈や生前贈与のような被相続人自身の財産処分とは同視しがたいという意味と考えられるでしょう。
例外的に特別受益に準じた取り扱いを受ける
しかし、上記最高裁決定は、次のように述べて、特別受益制度の趣旨である「共同相続人間の公平」の見地から、保険金請求権についても特別受益に準じた取り扱いを受ける例外があるとの判断を示しました。
もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。
共同相続人間の不公平の考慮要素は
では、上記最高裁決定のいう「特段の事情」については、具体的にいかなる要素を考慮して判断することになるでしょうか。この点について、同決定は、次のような事情を総合考慮すべきとしています。
- 保険金の額
- 保険金の額の遺産に対する比率
- 保険金受取人である相続人及び他の相続人と被相続人との関係(同居の有無、被相続人の介護に対する貢献度)
- 各相続人の生活実態
個別事例における裁判所の判断
では、上記最高裁決定の基準は、具体的な個別の事例においてどのように適用されるでしょうか。これはつまり、どの程度の事情があれば、相続人間の不公平が特別受益制度の趣旨との関係で是認できなくなるのかという問題です。以下では、同決定以降、生命保険金についての特別受益性を判断したいくつかの裁判例の概要をみておきましょう。事例数が少ないためハッキリとした境界線が引けるわけではありませんが、ある程度の感覚はつかめると思われます。
事情
- 保険金の額:約574万円
- 遺産に対する比率:10%弱
- その他:受取人が被相続人と同居。被相続人の夫の介護を手伝う。
結論
- 特別受益に準じた持ち戻しを否定
事情
- 保険金の額:約1億0129万円
- 遺産に対する比率:約100%
- その他:受取人変更当時、受取人と被相続人との同居がなく、被相続人夫婦の扶養や介護を託するといった明確な意図は窺われない。
結論
- 特別受益に準じた持ち戻しを肯定
事情
- 保険金の額:約5154万円
- 遺産に対する比率:約61%
- その他:受取人と被相続人の婚姻期間は3年5ヶ月程度
結論
- 特別受益に準じた持ち戻しを肯定
事情
- 保険金の額:2100万円
- 遺産に対する比率:
- 相続開始時の遺産評価額(772万3699円)の約2.7倍
- その他:
- 保険金額は一般的な夫婦間の生命保険金額と比較して特に高額ではない
- 被相続人と相手方(受取人)は婚姻期間約20年、同居期間約30年の夫婦
- 相手方は専業主婦で、被相続人の収入以外に収入を得る手段がなかった
- 保険契約は相手方との婚姻を機に受取人変更・減額されている
- 相手方は54歳の借家住まいで、長期的な生活保障が必要
- 抗告人(他の相続人)は被相続人と長年別居し、生計を別にしていた
結論
- 特別受益に準じた持ち戻しを否定
事情
- 保険金の額:1475万6880円
- 遺産に対する比率:
- 相続開始時の遺産総額(1579万2746円)の約93%
- その他:
- 被告(受取人)は被相続人の養子で、財産管理や介護等に貢献。原告(他の相続人)は被相続人から離縁を求められていた。これらの事情を考慮しても特別受益に準じた扱いをすべき特段の事情あり。
結論
- 特別受益に準じた持ち戻しを肯定
まとめ
上記のとおり、保険金の受領が例外的に特別受益と同視されるかは、当事者の関係等も含めた個別具体的事情を総合して判断されることになりますが、基本的には、遺産の総額に対する保険金額の比率が一定程度を越えると、保険金が特別受益に準じた取り扱いを受ける可能性は高まる ものといえます。
このため、上記の比率からして生命保険金の特別受益性が問題になりそうな遺産分割に臨む場合、相続人としては、どちらの立場に立つにせよ、自身の主張の根拠となる事情とその裏付け資料をあらかじめ調査・整理しておくとよいでしょう。
他方、生前の被相続人が、遺産分割とは関係なく、高額な生命保険金を特定の相続人に受け取らせたい場合には、死亡保険金は持ち戻しの対象とならないという原則論だけに依拠するのではなく、これが特別受益に準じて扱われる事態も想定して、遺言等により持ち戻し免除の意思表示を残しておくことが重要です。