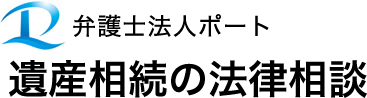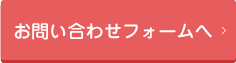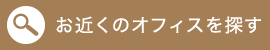相続放棄の期間制限とその実践的対処法
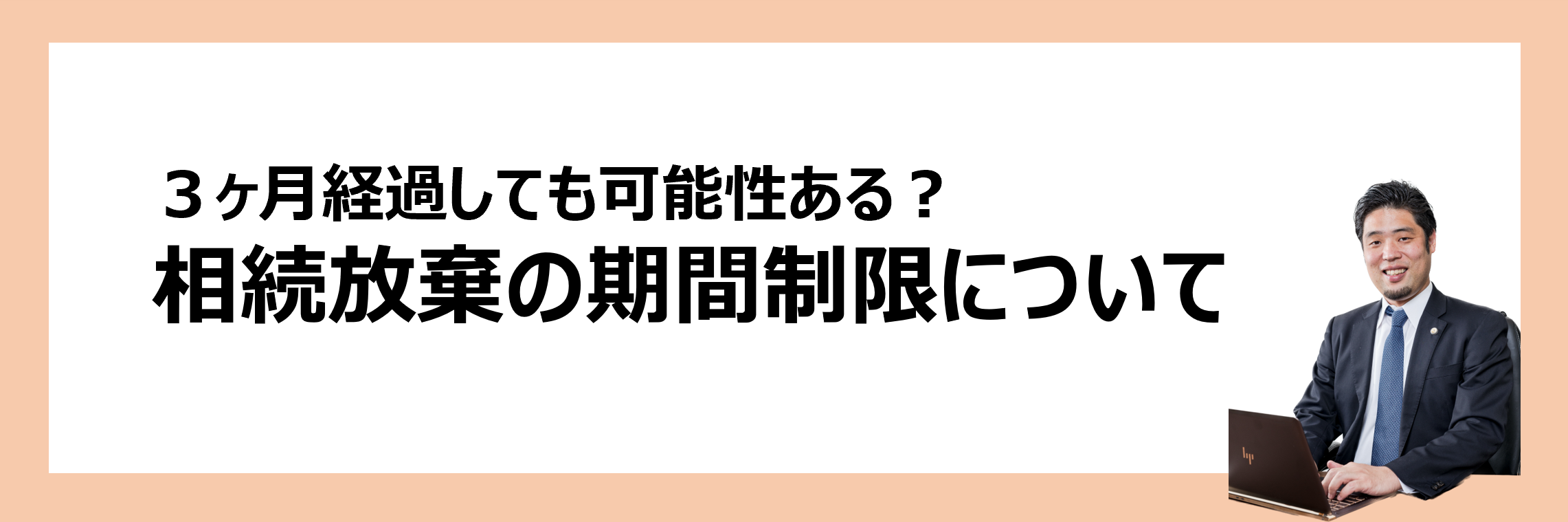
相続人となった人は、自らの意思で相続を放棄することによって、被相続人の権利・義務を受け継ぐことを拒否できる。これが相続放棄という制度です。
ただし、この相続放棄を行うには期間制限があります。ここまではの話は比較的よく知られていますが、その具体的に内容について正確に知っているという方は少ないかもしれません。
相続放棄をできる期限はいつまでで、どのような状況で延長されるのか。また、特別な事情がある場合に、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合はあるのか。
本記事では、相続放棄の期間の原則と例外について、相続放棄を取り扱う弁護士が裁判事例や実践的なアドバイスとともに詳しく説明します。
相続放棄の期間制限に関する原則と例外
原則:「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」3ヶ月以内
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、その相続について次のいずれを選択するかを決定し、必要な手続きをとらなければなりません。
- 単純承認:被相続人の権利義務を無限に承継する。特別手続の必要はない。
- 限定承認:相続人の積極財産の範囲で消極財産を承継する。家庭裁判所への申述手続きが必要。
- 相続放棄:被相続人の権利義務を一切承継しない。家庭裁判所への申述手続きが必要。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
引用元:e-Gov法令検索
ここで、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が亡くなったことだけでなく、これに加えて、自身がその相続において相続人となることを知った時のことをいいます(最高裁昭和57年(オ)第82号同59年4月27日第二小法廷判決)。また、相続人が上記選択をするための調査や検討を行うべき期間のことを「熟慮期間」と呼ぶことがあります。
例外1:再転相続では再転相続人の認識を基準に起算
- 第1相続:Aが死亡しBが相続人
- 第2相続:Bが死亡しCが相続人
第1相続においてBが相続の承認や放棄について選択をしないまま、第2相続が起きるケースを再転相続といいます。こうした再転相続の事案では、Cは、第1相続、第2相続のそれぞれについて、相続放棄をするか承認するかを選択する必要があります。この場合の熟慮期間の起算点を、Bの認識を基準(Bが自己のためにAの相続が開始したことを知った時)に決めてしまうと、Cにとって第1相続の熟慮期間がほとんど確保できない状態となるおそれがあります。そこで、民法916条は、再転相続の場合には、第1相続についての熟慮期間はCの認識を基準に起算することで、第1相続について承認か放棄かを選択する機会を保障しています。
第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
引用元:e-Gov法令検索
なお、令和元年8月9日最高裁判決によれば、民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、第2相続の相続人(C)が、第1相続における相続人としての地位を自己が承継した事実を知った時を意味するとされています。
例外2:相続人が未成年者または成年被後見人であるときは法定代理人の認識を基準に起算
熟慮期間は、相続人が、相続財産調査を行い相続の放棄又は承認のどちらを選択するかについて十分な検討を行う機会を保障するために、相続人に与えられた期間です。
このため、判断能力が十分でない未成年者や成年被後見人が相続人となっているケースでは、相続人に代わって相続財産の調査や検討をなすべき法定代理人が、未成年者や成年被後見人のために相続が開始したことを知った時を基準として熟慮期間を起算するものとされています。
第九百十七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
引用元:e-Gov法令検索
相続放棄の期間制限を過ぎたらどうなるか
相続放棄の熟慮期間内に相続放棄や限定承認を行わない場合、相続人は相続を単純承認したと見なされます(民法921条2号)。
このため、相続人が相続放棄の申述を熟慮期間経過後に行っても、原則として、その申述は家庭裁判所に受理されず、相続放棄は認められません(こうした場合に、相続放棄に期間制限があることを単純に知らなかった等の事情は、通常、家庭裁判所に考慮してもらえません)。
そして、単純承認の場合、相続人は被相続人の権利義務を無限に承継することになりますので、相続人は自身が受け継いだ被相続人の債務については、相続人固有の財産を持って返済する義務を負うことになります。
つまり、被相続人に多額の負債があるような場合に相続放棄の手続きを忘れてうっかり熟慮期間を経過してしまうと、相続人は固有の財産を持って負債の返済を強いられるという極めて深刻な事態を招くことになり得ます。
相続放棄の期間制限に関する弁護士からの実践的アドバイス
ではこのような深刻な事態を回避するために、相続放棄を検討している相続人はどのような対処をすれば良いでしょうか。ここでは、相続放棄を検討している相続人の読者の方へ向けて、三つのポイントを紹介したいと思います。
できる限り相続開始後3ヶ月以内の手続きを
まず一つ目は、相続放棄を行う場合には、できるかぎり、「被相続人の死亡から」3か月以内に相続放棄の申述を済ませてしまうことをお勧めします。
前述のとおり、民法が定める熟慮期間はあくまで相続人が「自己のために相続があったことを知った時」からスタートすると規定されています。したがって、相続開始=被相続人の死亡から3か月以上が経過していても、相続人が「自己のために相続があったことを知った時」から3ヶ月以内であれば、理論的には何ら問題はありません。
しかし、現実には、相続人が一定の事実を認識した時期を事後的に証明することは簡単ではありません。そこで、熟慮期間内であることを客観的に証明可能な、被相続人の死亡から3か月以内の時期に相続放棄の申述を済ませてしまうことが、債権者から熟慮期間の徒過について不必要な疑いをかけられず、トラブルに巻き込まれることを回避するという観点からはおすすめです。
熟慮期間伸長の制度を活用
二つ目は、熟慮期間伸長の申立ての活用です。熟慮期間の終期が迫っている相続人のうち、熟慮期間内に相続放棄をするか相続を承認するかの判断がつかない、相続放棄をしようと思うがその準備が間に合わないなどという事情がある方については、熟慮期間伸長の申立てを行い、これを裁判所に認めてもらうことによって、熟慮期間を一定期間延長することができます。
被相続人との元々の付き合いが薄い場合や、被相続人が幅広く事業を行っているようなケースでは特に、通常の熟慮期間である3ヶ月の間に相続放棄をするかどうかの判断をするのは想像以上に時間的な困難を伴うものです。家庭裁判所も、特に1回目の期間伸長については、相続人の実情に応じた柔軟な対応を行っているという印象がありますので、弁護士に相談するなどしてぜひ活用を検討していただければと思います。
3ヶ月を過ぎてしまっても自己判断で諦めない
三つ目は、仮に、相続放棄の熟慮期間が経過してしまったと思っても、自己判断であきらめてはいけないということです。少なくとも一度は、なるべく早く、弁護士に相談してみることをおすすめします。
実は、一見すると熟慮期間が経過してしまったように見える事案でも、最高裁判所やその他の裁判所が、熟慮期間の起算点を解釈により遅らせるというテクニックを使って、結論として相続放棄を認めるという判断をしているケースは複数あります。以下ではその一部を事案の概要とともに紹介します。
1)最高裁判所第2小法廷昭和59年昭和59年4月27日判決
この判決は、熟慮期間は相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つたときから起算するのが原則であるとしながらも、熟慮期間が相続人に与えられる趣旨に照らし、相続人が、上記の各事実を知った場合でも、そこから三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、
- 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、
- そのように信ずるについて相当な理由※1があると認められるとき
には、民法915条の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当であるとしました。
その上で、こうした規範に以下のような事実関係を当てはめて、結論として被上告人らによる相続放棄は熟慮期間内になされたものであると認め、相続債権者である上告人の請求を退けた高裁判決を支持しています。
人物関係
- 被相続人:亡D
- 相続人:B1,B2,B3(亡Dの子)=被上告人
- 上告人:亡Dに対する債権者
事案の概要
- 昭和41年春: 被上告人B1が家出する
- 昭和42年秋: 亡Dの妻が被上告人B2、B3を連れて家出する(以後、親子間の交流は断絶)
- 昭和52年7月25日:第一審被告である亡Dは、上告人との間で、Eの支払いに関する1,000,000円の準消費貸借契約上の債務について連帯保証契約を締結
- その後、亡Dは生活保護を受けて生活。
- 昭和54年夏: 上告人が亡Dに保証債務の支払を求める本件訴訟の係属中に亡Dが入院
- 被上告人B1は亡Dの入院を民生委員から知り、入院中に見舞うが亡Dの資産や負債について説明を受けなかった。
- 昭和55年2月22日:第一審裁判所は上告人が亡Dに対して連帯保証債務を求める訴請求を認容する判決
- 昭和55年3月5日:亡Dが判決正本の送達前に死亡(被上告人B1、B2、B3は当日または翌日に亡Dの死亡を認識)
- 昭和55年7月28日:上告代理人が受継の申立をする
- 昭和56年2月9日:第一審裁判所は、亡Dの相続人である被上告人について訴訟手続の受継決定をする
- 昭和56年2月12日:被上告人B1に対して第一審判決正本を送達
- 昭和56年2月13日:被上告人B2に対して第一審判決正本を送達
- 昭和56年2月14日:被上告人B3は被上告人B2から送達の事実を知らされた(その後3月2日にB3にも送達)
- 昭和56年2月26日: 被上告人らが大阪家庭裁判所に相続放棄の申述をする
- 昭和56年4月17日: 家庭裁判所が相続放棄の申述を受理する
この判決では、被相続人が生活保護を受けており、相続人との交流も長期間断絶していたという事情から、相続による相続債務を含めた相続財産の正確な調査を期待することは著しく困難であろうという点を重視し、相続人の保護を図ったものと理解されます。
※1 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況を考慮要素とする。
2)東京高等裁判所平成19年8月10日決定
上記の最高裁判決では、熟慮期間の起算点を原則よりも遅らせることのできる要件として、相続人が被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていたことを要求していました。しかし、本決定は、この基準をやや緩和し、相続人において「被相続人に積極財産があると認識していてもその財産的価値がほとんどなく、一方消極財産について全く存在しないと信じていた」という場合にも、そのように信じたことにつき相当な理由があれば、熟慮期間は、相続人が消極財産の全部又は一部の存在を認識したとき(またはこれを認識し得たであろうとき)から起算するという判断を示しました。
その上で、以下のような事実関係の相続人について、熟慮期間内の相続放棄申述があったものと認め、これを受理する決定をしました。
人物関係
- 被相続人:母Aの六男
- 相続人:母A
- Aの夫(被相続人の父):亡C
事案の概要
- Aの夫Cは平成5年に死亡。Cの相続人はAと6人の息子であった。
- Cの相続人たちは遺産分割協議を行い、Aは宅地を、被相続人は本件相続財産(土地)と100万円を受け継いだ。
- 本件相続財産は、高圧送電線用鉄塔に隣接する土地で、単独での資産価値はほとんどない
- 被相続人が平成17年12月17日に死亡。相続人はAのみであった。
- Aは、被相続人死亡時に被相続人の死亡と自分の相続開始を知った。
- 当時、Aは95歳、耳が悪く物忘れがあるが、物事の判断能力はある。被相続人との付き合いはほとんどなかった。
- Aは被相続人の死亡時に相続財産があることは知っていたが、負債があることは知らなかった
- Aは、親族から相続財産の登記事項を入手したところ、被相続人が債務に対して連帯保証をしていたことが判明。債務の残元本は1,200万円に達しており、超過利息を含めても600万円を下回らない。
- Aは平成18年6月20日に相続放棄申述を行った
このように、一見熟慮期間が経過してしまっているように見えたとしても、個別の具体的な事情によっては、熟慮期間の起算点を解釈によって遅らせることにより、これを適法な相続放棄として取扱うことのできる事案が存在します。もちろん全ての事案がこのような救済的判断を受けられるということではありませんが、少なくとも自分一人の判断で諦めることなく、専門家に相談してみるということが重要です。
まとめ:相続放棄は弁護士への相談・依頼がおすすめ
以上、相続放棄の期間制限について解説しました。
相続放棄は自分でできる手続きと言われることもありますが、少しのうっかりミスで、意図しない重大な結果を招くこともあります。このような相続放棄を弁護士に相談することで、あなたは正確な情報を入手し、適切な手続きを着実に実施することができます。特に、期限が差し迫った相続放棄や、熟慮期間を経過してしまったように見える事案では、弁護士に相談することで、何らかの解決方法が見つかる可能性もあるでしょう。
このような意味で、相続放棄問題については、相続問題を得意とする弁護士に相談・依頼することをおすすめします。当事務所においても、相続放棄申述手続きの代理業務を承っておりますので、是非お問い合わせください。
関連サービス