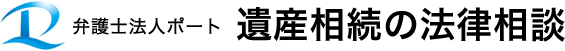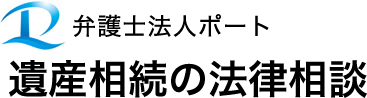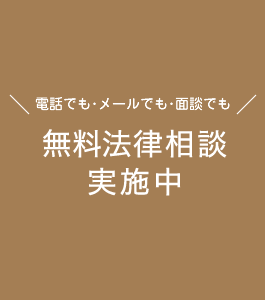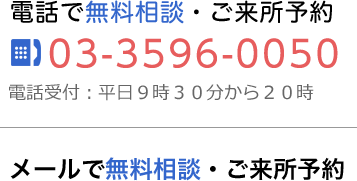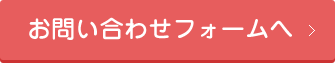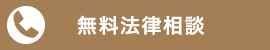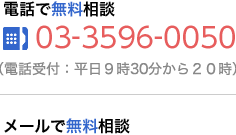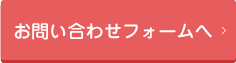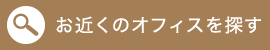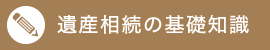交渉・調停・訴訟?遺留分侵害額請求事件が解決するまでの流れ
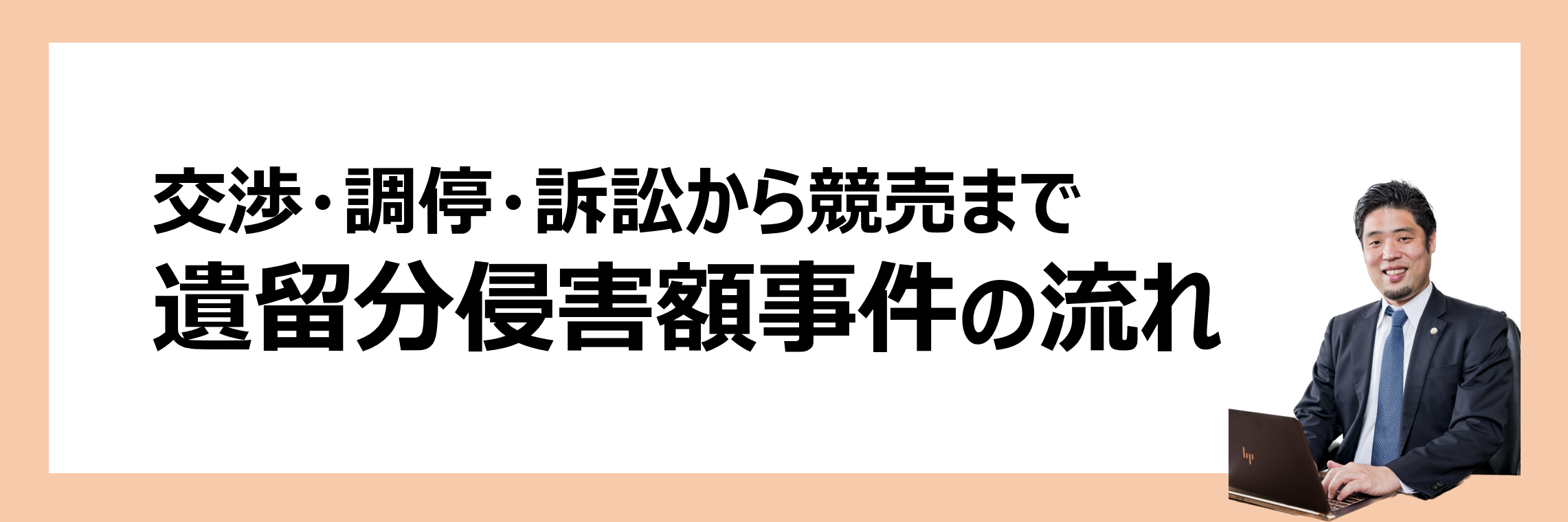
遺留分とは、法律によって定められた「相続人が最低限受け取るべき取り分」を意味します。特定の相続人に極端に有利な内容の遺言書が発見されたり、多額の生前贈与がなされていた場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。これによって本来確保されるはずの取り分を、金銭で取り戻す仕組みになっているのです。
しかし、いざ請求を行っても、請求の相手方が金額の算定方法に異議を唱えたり、話し合いに全く応じなかったりすることがあります。このように、一筋縄ではいかないケースも少なくありません。実際、多くの方にとって「遺留分侵害額請求」は人生で一度あるかないかの法的手続きであり、どのように手続きを進めればよいのかイメージが湧きにくいのが現実です。
そこで本記事では、遺留分権利者の立場から見た「遺留分侵害額請求がどのような手続きを経て解決に至るのか」を、交渉・調停・訴訟それぞれの段階で整理しながら解説します。実務で多くの遺留分案件を扱ってきた弁護士の視点を交えながら、流れをわかりやすくご紹介します。
遺留分侵害額請求通知書の送付
遺留分侵害額請求事件では、遺留分権利者が侵害額請求権を行使して初めて、被相続人から遺贈や生前贈与を受けた遺留分義務者に対する金銭債権が発生が発生します。
そこで、まずは遺留分侵害額請求の相手方に対して、遺留分侵害額請求を行使するとの意思表示を通知します。なお、遺留分侵害額請求権の行使には期間制限(消滅時効や除斥期間)がありますのでご注意下さい。
遺留分侵害額請求通知書の作成方法
通知書の形式そのものは法律で決まっていないため、ポイントを押さえていれば自由に作成できます。ただし、下記のような点を意識するとトラブル回避に役立ちます。
- 遺留分侵害額請求をする旨をはっきり記載する
例:「あなたが受け取った生前贈与(または遺贈)によって、私の遺留分が侵害されていますので、遺留分侵害額請求をします。」 - 請求金額を提示する(可能な場合)
例:「○○円について支払いを求める」
もっとも、遺産の範囲や評価額がまだ確定していない段階では、金額を明記せず「遺留分侵害額請求を行う」という意思表示だけにとどめることもあります。 - 配達証明付き内容証明郵便で郵送する
実際に通知書を送った事実と、送った日時を確実に証明できるようにしましょう。これが後々、消滅時効成立前に請求を行使していたという重要な証拠になります。
遺留分侵害額請求通知の相手方
民法上、遺留分侵害額請求の相手方となるべき者(遺留分義務者)の範囲や順序は詳細に定められています。たとえば「まずは受遺者に請求し、足りなければ生前贈与を受けた者に請求する」といったルールがあります。この順序を間違えると、本来の請求先への権利行使が時効によって失われるリスクがあるため、十分な注意が必要です。
関連記事:誰が支払いを負担する?遺留分侵害額請求の相手方・請求先
遺留分権利者は、上記のルールに沿って遺留分侵害額請求をなすべき相手方を特定し、正しい請求先に遺留分侵害額請求を行わなければなりません。この点は専門家に相談しながら、対象を誤らないように正確に特定しましょう。
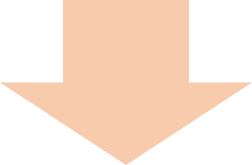
裁判外での交渉による解決
内容証明郵便にて遺留分侵害額請求の意思を示したら、まずは裁判外での交渉を試みるのが一般的です。両者の話し合いで、金額や支払時期、支払い方法などに合意ができれば、合意書を作成することで決着を図ります。
-
財産評価で意見が対立
遺留分を計算するには、被相続人が残した財産の種類や評価額を正確に把握しなければなりません。特に不動産を多く持っていた場合、不動産評価額についての認識が大きく異なることもあります。また、非上場株式などの評価も難しく、専門的知識が求められます。
-
遺言書の有効性や解釈に争い
遺言書の形式的要件が不備であったり、真偽が疑われる場合など、請求以前に「そもそもこの遺言は有効かどうか」という争点が発生する場合があります。このような争点を裁判外で解決するのは難しいこともあり、訴訟や調停に進まざるを得ないことも珍しくありません。
裁判外交渉のメリットは、話し合いによる柔軟な解決が可能という点です。裁判所を通さないため、時間や費用をある程度節約できます。一方、交渉がこじれてしまうと、当事者間だけでは解決が難しくなるため、早期に見切りをつけて調停や訴訟に移行することも大切です。
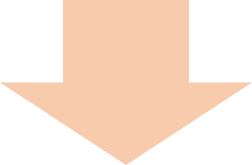
家庭裁判所における家事調停による解決
遺留分侵害額調停を申し立てるのが原則(調停前置主義)
裁判外での交渉が上手くいかなかった場合、まずは家庭裁判所の調停手続を利用して遺留分侵害額請求の問題解決を図ることになります。
法律上、遺留分に関する問題は「家庭に関する事件」の範疇に含まれるため、いきなり訴訟を起こすのではなく、まずは調停を申し立てる必要があります。これを調停前置主義と呼びます。
ただし、例外として当事者同士の対立が激しく、まったく話し合いが期待できない場合などは、調停を経ずに訴訟へ進むことを認める運用も存在します。実際に、相手方が連絡を拒絶しており「調停になっても無駄」と考えられるような事案では、いきなり訴訟を提起するケースもあるのです。
家事事件手続法
第二百五十七条 第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。
2 前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。
3 裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。
引用元:e-Gov法令検索
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停申立書を提出
原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺留分侵害額請求調停(裁判所の外部サイトにリンクします)を申し立てます(当事者間の合意があれば他の家庭裁判所も可)。申立書には「申立の趣旨」「申立の理由」「当事者の住所氏名」のほか、被相続人の戸籍等、遺言、遺産の内容を確認できる資料などを添付します。
書類が受理されると裁判所が調停期日に当事者を呼び出します。調停期日では、調停委員という第三者が間に入り、両者の意見をすり合わせながら解決の糸口を探します。
裁判所を介して話し合いを進め、まとまれば調停調書を作成
調停は、双方の意見を裁判所が調整してくれるため、裁判外交渉よりも合意形成に至る可能性が高まります。調停期日においては、調停室に各当事者が順番に入室し、調停委員と個別に話をする方式が一般的です。調停委員が提案する折衷案を交えながら、双方が妥結可能な解決のための落としどころを検討していくのです。
調停のメリットは、合意内容が「調停調書」という公的な文書にまとめられ、それ自体が判決と同じ効力を持つことです。調停成立後に相手が支払を拒否した場合でも、すぐに強制執行の手続きを進めることができます。また、話し合いベースであるため、感情的にも受け入れやすい着地点が見つかることが少なくありません。
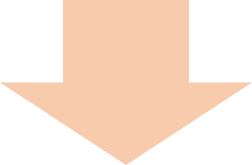
遺留分侵害額請求訴訟(裁判)による解決
家庭裁判所での調停が不成立(もしくは調停をせずに)となった場合は、最終的に地方裁判所(または簡易裁判所)で訴訟を起こすことになります。原告となる遺留分権利者が、受遺者や受贈者を被告として「○○円の支払いを求める」と訴状を提出し、正式な審理が進んでいきます。
-
訴状提出・被告の答弁書等による争点整理
原告が訴状を提出すると、被告側も答弁書や反論資料を提出し、その後、双方の主張を記載した準備書面のやりとりがなされ、これにより争点が明確化されます。遺産評価の根拠や遺言の有効性、生前贈与の時期や金額など、具体的な争いが本格化します。 -
証拠調べ(書証・証人尋問など)
遺留分の計算には多数の資料が必要であるため、不動産評価に関する資料のほか、預貯金通帳や取引明細などを証拠として提出します。必要に応じて証人尋問が行われ、事実関係が立証されます。 -
和解交渉・判決
訴訟中であっても、裁判所は折に触れて和解を勧めることがあります。和解で合意できれば、訴訟上の和解として確定判決と同様の効果を持ちます。合意に至らない場合は、最終的に判決が言い渡され、原告勝訴の場合は被告に金銭支払いが命じられます。
また、日本の裁判制度は三審制であるため、地方裁判所の判決に納得がいかなければ高等裁判所→最高裁判所へと上訴することが可能です。ただし、控訴審・上告審に進むほど時間も費用もかかるため、当事者の負担は大きくなります。
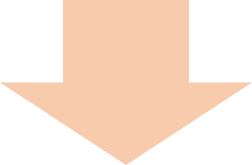
強制執行手続き
最終的に「支払いをせよ」という判決が確定したにもかかわらず、被告が支払いを拒否した場合は、強制執行を申立てることで相手方の財産を差し押さえることができます。預貯金、不動産、株式などを差し押さえて競売にかけ、その売却代金を遺留分権利者に配当させる流れです。
なお、2019年の民法改正により、遺留分は「お金」で取り戻す方式(遺留分侵害額請求)に一本化されたため、判決を得たのちもスムーズに強制執行手続きへ移行しやすくなりました。改正前の制度とは異なり、返還すべき財産の現物を直接取り戻すのではなく、金銭請求として確定判決を得れば強制執行が可能です。
まとめ
遺留分侵害額請求は「請求通知→交渉→調停→訴訟→強制執行」というおおまかな流れで進みます。ただし、実際には当事者間の関係性や遺産の種類によって、手続きに要する時間・労力や優先すべき対応が大きく変わってきます。
- 交渉段階で円満解決が見込めるのか
- 調停に至ったとしても話し合いの余地はあるのか
- 訴訟に発展してしまうと覚悟しなければいけない時間や費用
- 最終的には強制執行も視野に入れる必要があるのか
これらをトータルで判断しながら、できるだけ早いタイミングで専門家に相談することが、スムーズな問題解決の近道といえるでしょう。
弁護士法人ポートでは、遺留分事件の実務経験豊富な弁護士が、遺留分侵害額の算定から交渉・調停・訴訟のサポートまで一貫してお手伝いしています。遺留分に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所の無料相談をご検討ください。